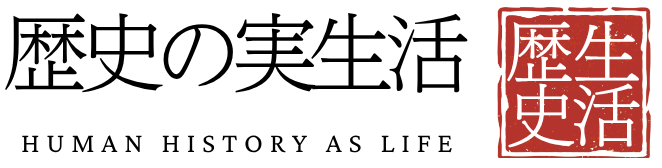江戸の町に欠かせない銭湯。
その裏で一日中、火と煙にまみれ、町人たちの疲れを溶かしていたのが“風呂焚き”だった。
■ 夜明け ― 火を起こす
まだ闇の残る明け方。
銭湯の裏手に、かすかな火の音がする。
「ぱち、ぱち」と薪がはぜる。
風呂焚きの徳松が、火を見つめていた。
「湯は人の気分と同じでな、急に熱くしちゃいけねぇ」
彼の指先は火の色で温度を測る。
温度計なんてものはない。
炎の揺れ、湯気の立ち方、煙の匂い――
それが彼の仕事の道具だった。
湯が静かに音を立て始めると、町が動き出す前の江戸の空に、煙がゆっくりと上がっていく。
■ 朝 ― 一番風呂の支度
夜明けとともに、銭湯の戸が開く。
「さあ、湯ができたぞー!」
桶を抱えた男たちが笑顔で入ってくる。
徳松は火口を見張りながら、湯の温度を一定に保つ。
熱すぎれば怒鳴られ、ぬるければ文句を言われる。
けれど、誰もが湯に入って一言、「ああ、いい湯だな」と漏らす瞬間、その言葉が、彼の一番の褒美だった。
■ 午前 ― 炭と汗の匂い
火室の中は灼熱地獄だ。
薪をくべるたび、顔に熱風がぶつかる。
髪は焦げ、肌は煤で真っ黒。
それでも徳松は笑う。
「火に好かれりゃ、風呂が喜ぶ」
煙が目にしみても、彼は手を止めない。
外では、
「湯屋の煙が上がると、今日もいい天気だ」
と町人が言う。
彼は知らぬところで、江戸の“天気”をつくっていた。
■ 昼 ― 湯気の中の小さな町
昼どき、銭湯は人であふれる。
商人、職人、子どもたち。
湯屋の中は、まるで別世界。
風呂焚き場から聞こえる声は、笑いと喧嘩が半々だ。
「火消のやつらがまた自慢話してやがる」
「大工がうるせぇと思ったら、長湯してんのか」
徳松は湯気越しに町の人間模様を感じ取る。
湯を沸かすだけではない。
人と人の距離を温めるのが、風呂焚きの役目だった。
■ 夕刻 ― 湯の息づかい
日が傾く。
一日の終わりを知らせるように、徳松は焚き口の灰をかき出す。
火が静まり、湯の表面が穏やかになる。
外からは、風呂上がりの笑い声。
桶の音、暖簾のはためく音。
徳松は火箸を置き、湯気の向こうに沈む夕陽を眺める。
「今日も、町があったまったな」
その一言に、煤まみれの笑みがこぼれる。
■ 夜 ― 火とともに眠る
銭湯の灯が落ち、人の声が消える。
徳松は灰の中に残る小さな赤を見つめる。
手を伸ばし、そっと火をつぶす。
残り香のように漂う湯気が、一日の終わりを告げていた。
「明日の湯も、ええ湯にしてやるさ」
そう呟いて、火室の壁に背を預ける。
熱を抱いたまま、眠りに落ちる。
■ ナレーション(締め)
火を操る者がいて、湯が生まれた。
湯が生まれて、人が笑った。江戸の銭湯の裏には、名もなき“湯守”たちがいた。
――湯を守り、町をあたためる。
それが、江戸の風呂焚きの仕事であり、生きた証だった。
次回はも乞うご期待!
参考・参照リンク(江戸時代)
※本カテゴリの記事は上記の史料・展示情報を参考に再構成しています。
江戸の一日シリーズ
-

江戸・船頭の一日|川が道で、風が友だった
水の都・江戸を流れる川を行き来し、人と荷と、時には運命までも運んだ男たちの物... -



江戸・左官の一日|土を塗り、壁に息を吹き込む
火に焼かれ、水に晒され、それでもまた立ち上がる町。その命をもう一度形にするの... -



江戸・傘張り職人の一日|雨を待つ者たち
雨が降ると、町が動く。晴れの日は、仕事が止まる。“天気商売”と呼ばれた傘張り職... -



江戸・按摩の一日|闇を歩き、人を癒やす
光の届かぬ路地を、音と気配で歩く。見えぬ目で町を見つめ、触れる指先で心を知る... -



江戸・風呂焚きの一日|湯を守り、町をあたためる
江戸の町に欠かせない銭湯。その裏で一日中、火と煙にまみれ、町人たちの疲れを溶... -



日本橋魚河岸を舞台にした「魚荷人足(うおににんそく)」の一日
――時代は文政年間。江戸の町が最も賑わっていた頃の情景です。 ■ 江戸・日本橋魚河...