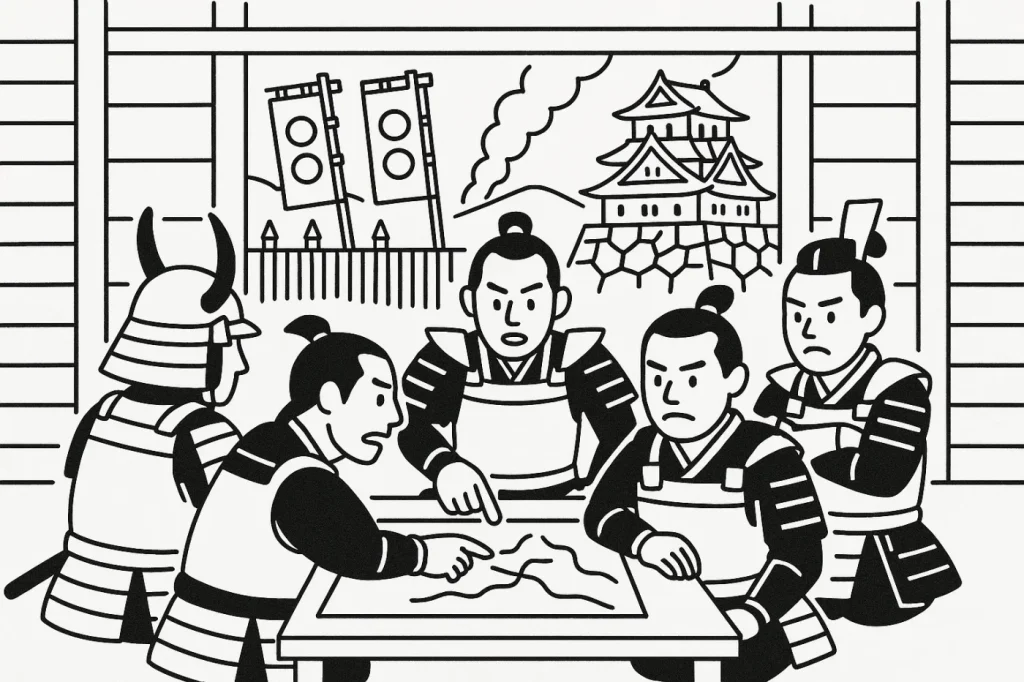秀吉の中国大返しって実話?あれだけの軍勢を短期間で200kmも移動させるのは、無理筋やろ?しかも計画的にではなく、突破発的にやで。
「中国大返し(ちゅうごくだいがえし)」は、まさに戦国時代の兵站(ロジスティクス)戦略の最高傑作です。
普通なら不可能な“遠征軍の逆走”を、わずか10日ほどでやってのけた。しかもそのスピードが、天下を決めたんです。
では、順を追って説明します。
そもそも「中国大返し」とは
時代は1582年(天正10年)。
織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」の直後の話です。
当時、羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)は、備中高松城(岡山県)で毛利軍と対峙していました。
信長から「西国を平定せよ」と命じられての遠征です。
ところが――本能寺で信長が討たれたという急報が届く。
普通なら、
「主を失った遠征軍」は混乱し、撤退中に敵に襲われて壊滅する
はずなんですが、秀吉はそこから“常識外れのスピードで畿内に引き返した”。
それが「中国大返し」です。
なぜすぐ戻れたのか?奇跡の兵站管理
秀吉の強みは「兵站と情報の管理能力」でした。
毛利軍との講和を即座に成立させる
信長の死を知った秀吉は、毛利軍と戦い続けるのは危険と判断。
そこで「信長の命令により戦いは終わり」と偽って和睦を提案。
敵に悟られずに撤退の口実をつくった。
補給線を整備していた
秀吉は日頃から遠征の際、街道ごとに兵糧の集積地を置くという準備をしていた。
つまり、「いつでも戻れるルート」を作っていた。
これがあったから、通常2〜3週間かかる道のりをわずか10日で踏破できた。
住民協力と銭の力
道中の村や宿場に「兵糧買い上げ」の命を出し、現金をばらまいて補給を確保。
これができたのは、信長時代に貯めた金と、秀吉自身の信用による。
“金で兵站を動かす”という、当時としては画期的なやり方でした。
移動ルートとスピードの異常さ
移動距離は約200km。
備中高松 → 姫路 → 明石 → 大坂 → 山崎(京都南部)。
雨の中、ぬかるんだ街道をわずか10日(6月6日〜6月13日)で走破。
兵1万〜2万を動かしたとされます。
普通なら1日10kmで限界。
それを20km以上で進んだ計算です。
馬や徒歩の混成軍でこの速度は近代でも異常レベル。
兵の疲労も相当だったはずですが、士気を維持したのは秀吉の「報復の大義」でした。
「殿を討った仇を討つぞ!」という正義の名分が、軍の統率を保った。
そして「山崎の戦い」で光秀を撃破
10日後、山崎(現在の大阪府島本町〜京都府長岡京市付近)で両軍が激突。
明智光秀は油断しており、兵も疲れていた。
秀吉軍の勢いは圧倒的で、光秀は敗走し、のちに討たれます。
これで秀吉は「信長の後継者」として一気に台頭します。
なぜこの行動が伝説になったのか
情報戦の速さ:報告→決断→講和→出発まで半日以内
兵站戦の巧みさ:補給線の事前整備+資金力
心理戦の妙:敵味方ともに“動揺”を制した
つまり秀吉は、単に「足が速かった」のではなく、情報・補給・士気・政治を一体化して動かした。
まさに「戦国のサプライチェーン・マネジメント」なんです。
参考・参照リンク(戦国時代)
※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。