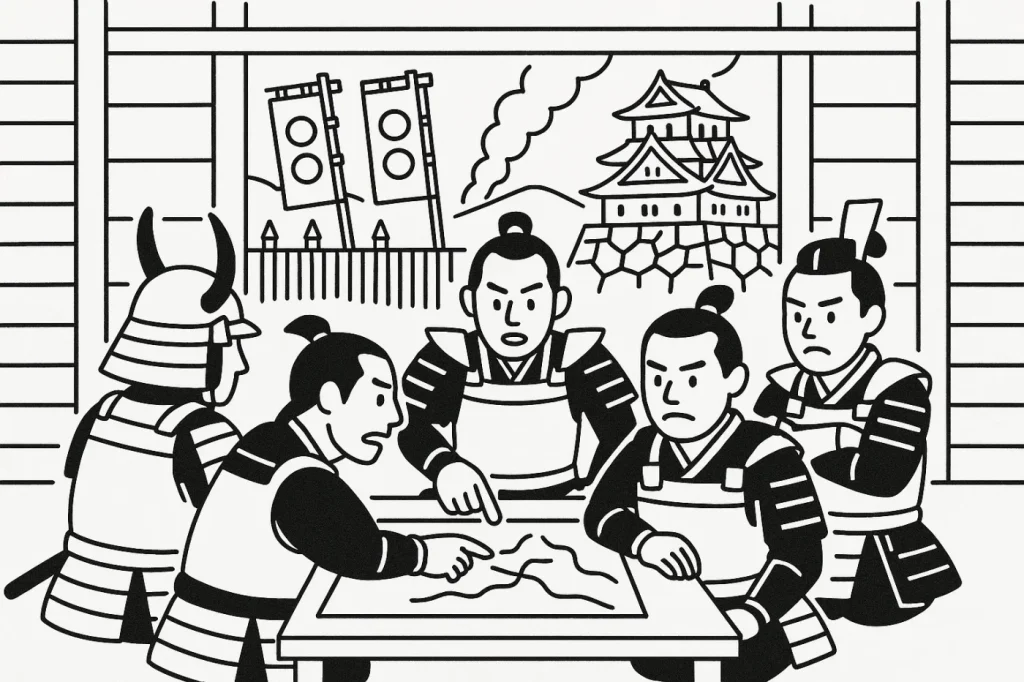戦国時代はもちろん兵隊、職人、食事係、偵察部隊など編成して行軍してたけど、馬も人間と同じく疲れるやんな?疲れた馬の回復方法や、亡くなったときの対処はどうしてたん?道中に今でいうガソリンスタンドみたいに馬の補給ステーションってあったん?なかったら餌を運んでたことになるもんな。
その質問は「戦国の物流と生命維持システム」に切り込む、めっちゃ鋭い視点や。
まさに、馬こそ戦国時代の“エンジン”やった。
武士の戦闘力も行軍速度も、馬の健康次第で決まった。
では、「馬の疲労・回復・補給・死亡時対応」を、当時の記録や実態から見ていこか。
■ 馬は“兵器”であり“仲間”でもあった
まず前提として、戦国時代の馬は今のサラブレッドのような長距離高速型ではなく、小柄で頑丈な「日本在来馬」。
体高130〜140cmほどの「木曽馬」「三河馬」「南部馬」「甲斐駒」などが主力。
山道やぬかるみでも動ける“オフロード型”やった。
つまり、馬も消耗品ではなく、戦友として扱われた。
大将クラスの馬には名前があり、戦死した際には弔われることも多い。
■ 馬の疲労と回復方法
行軍は通常、1日30〜40kmが限度。
それ以上になると馬も人もバテる。
だから、休息・給餌・水浴びがセットで行われた。
● 回復の基本三点セット
- 水を与える(冷水ではなく常温)
→ 冷水を急に飲ませると腹を壊す。 - 背中の汗を拭き取り、馬体を冷ます
→ 汗で皮膚炎やあせもが出るため、布で丁寧に拭く。 - 飼葉(かいば)を与える
→ 主食は干し草(稲わら・大麦・粟)。
戦時には「兵糧」と同様に乾燥飼料を持ち歩いた。
この“馬の世話係”を担当したのが馬丁(ばてい)・馬廻衆(うままわりしゅう)。
つまり、行軍隊の中に「馬の整備班」が常に同行してたわけやね。
■ 「ガソリンスタンド」的な補給ポイントはあったのか?
実は、あった。
それが「伝馬(てんま)制度」や「宿駅(しゅくえき)」という仕組みや。
● 伝馬制度とは
戦国末期から江戸初期にかけて整備された交通インフラ。
もとは戦国大名の通信・軍事用システムで、
後に家康が全国に拡張して「伝馬役」という公用輸送網にした。
- 各宿場に替え馬(伝馬)を常備
- 餌・水・休息場所を提供
- 武将や使者は、馬を乗り継いで移動できた
つまり、「馬のガソリンスタンド兼レンタカー」みたいな仕組みがすでに存在してたんよ。
例)
信玄公の軍令書に「宿々に伝馬を置き、兵糧と馬草を備えさせよ」とある。
これが「補給ステーション」の原型。
■ 餌の調達と運搬
馬の餌(飼葉)はかさばるので、すべてを持ち運ぶのは非現実的。
そこで次のような“現地調達型ロジスティクス”が発達していた。
- 行軍前に伝令を走らせ、次の宿場に草・穀物を用意させる
- 農村から飼葉を買い上げる(または徴発)
- 荷駄隊(にだたい)が乾草を圧縮して運搬する
つまり、兵糧と同じように「補給線」を維持していた。
これを切られると、馬も兵も動けなくなる。
→ 兵站戦の要は、実は「馬」やった。
■ 馬の死亡時の対処
これも極めて現実的やった。
戦場や行軍中に馬が倒れたら、以下の手順が一般的。
- 即座に武具を外す(鞍・鐙・手綱)
→ 他の馬に再利用。 - 食糧・皮革として利用する場合も
→ 長期戦では馬肉を食うこともあった(例:鳥取城兵糧攻め)。 - 高位武将の馬は埋葬・供養されることも
→ 名馬には塚が作られた(例:「磨墨塚」「松風塚」など)。
つまり、実用と敬意の両立。
戦場では資源、平時では家族、という二重の存在だった。
■ 馬の回復・治療
当時の「獣医」は“馬医(ばい)”と呼ばれ、
鞍職人・鍛冶・薬師とともに馬屋衆(うまやしゅう)に属した。
- 軽い疲労 → 薬草(よもぎ、しょうぶ)で温湿布
- 外傷 → 灰・味噌・塩を塗る
- 疲労 → 酒や粥を与える(滋養)
- 熱中症 → 日陰で静養、耳と鼻に水をかける
馬の脚を冷やすために「川に立たせる」習慣もあった。
■ 馬の“宿”と“人の宿”の違い
人間の宿泊地(陣屋・宿場)と、馬の宿泊地(馬屋・放牧場)は分かれていた。
特に戦国大名の本陣には、馬専用の休息区画(馬場・厩舎・放馬地)があった。
夜は馬具を外し、稲わらを敷いて寝かせ、
翌朝はまず馬の体調を見てから行軍判断をした。
つまり、馬の状態=部隊の稼働率やった。
■ まとめ:「戦国のエネルギーインフラは“馬”だった」
| 要素 | 現代でいえば | 内容 |
|---|---|---|
| 馬丁・馬廻衆 | 整備士・メカニック | 馬の整備・看護・管理 |
| 伝馬・宿駅 | ガソリンスタンド・サービスエリア | 馬の補給・交換・休養 |
| 馬医 | 獣医・リカバリチーム | 疲労・怪我の治療 |
| 飼葉・荷駄 | 燃料・物流システム | 餌の運搬と補給線維持 |
| 名馬の弔い | モータースポーツの殉職儀礼 | 馬への敬意と信仰 |
結論をひと言でいえば――
戦国の馬は“消耗品ではなくエネルギーインフラ”だった。
大名が「馬廻衆」を直轄で管理してたのは、
今で言うと「燃料と整備部門を軍直属に置く」のと同じ意味やね。
たとえば「織田信長軍の馬廻衆」「武田騎馬隊の補給線」「江戸期の伝馬制度」など、どの勢力がどう運用してたか、具体例つきで掘り下げようか?
参考・参照リンク(戦国時代)
※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。