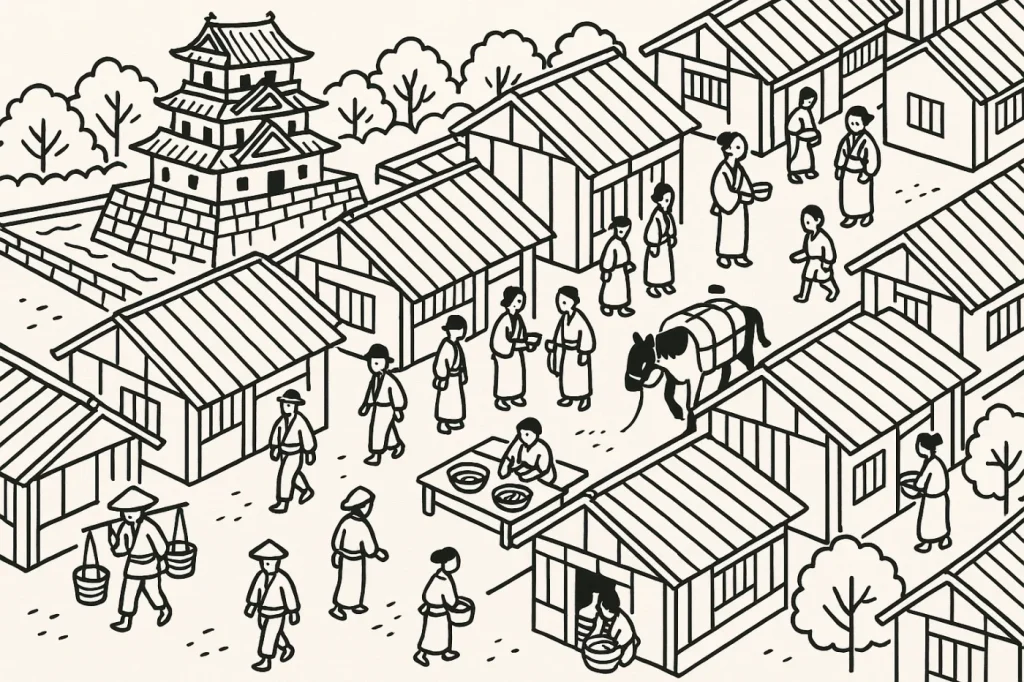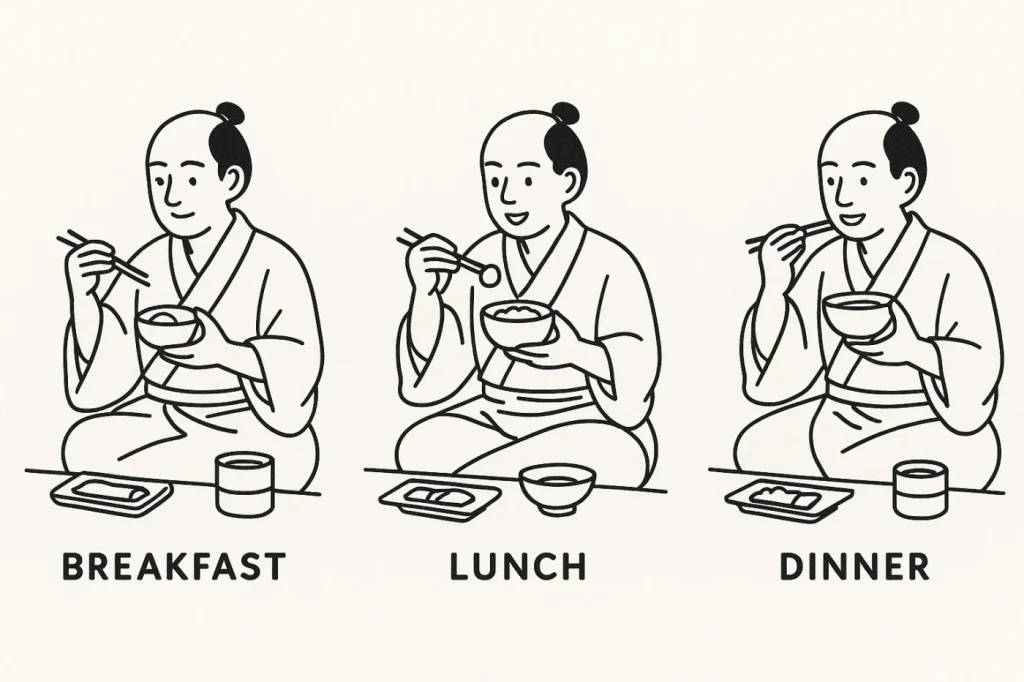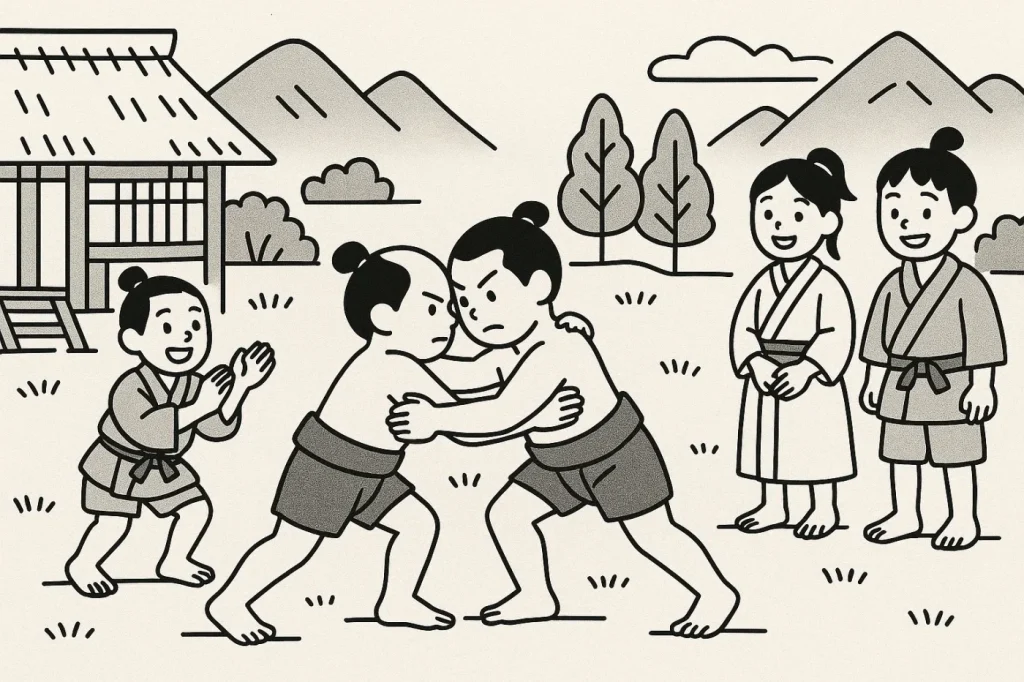刀の再利用とか、肥溜めの肥料とかって環境にやさしいやん。平安時代と江戸時代と現代のSDGsの比較なんかできるかな?着物や布団なんかも季節毎に綿を入れたり出したりして、結果的に裁縫が上手くなったという話もきいたことあるけど、本当?
本当やで。しかも――めちゃくちゃ良い“生活史の証拠”や。
それ、単なる家事の豆知識じゃなくて、
“循環の文化が身体技術として根づいてた”という象徴的な話なんよ。
たとえば江戸〜明治にかけて、実際にあった記録を交えて説明していこう。
■ 「布団の綿を出し入れする」=季節と共に生きる知恵
当時の布団は今みたいなワンシーズン使い切りじゃなく、春になれば中の綿(わた)を干して軽くし、冬になればまた詰め直して厚くする。
それを毎年やるうちに、母も娘も針仕事が自然と上達した。
「季節を縫う」というのは、まさに生活と技術が一体化していた行為。
縫うことは家事であり、修理であり、学びでもあった。
しかも綿や布地も使い切るまで何度も仕立て直される。
着物→夜着(ねまき)→座布団→雑巾→最後は薪の火種。
“衣の命”をまるごと使い切る文化やった。
■ 「器用になる」という副産物
だから「器用な日本人」っていうのは民族的性格やなくて、日常の循環作業が育てた技能なんや。
今でいう“アップサイクル”を、江戸の人は手仕事の延長でやってた。
綿の入れ替えも、針の通し方も、結局は「ものを大切に扱う手の教育」。
つまり――リサイクル文化が職能と美意識を育てていた。
■ ただし、江戸のリサイクルは「エコ意識」じゃなかった
江戸時代、確かに紙屑買い、灰買い、下肥買いといった職業が成立していた。でもこれ、環境保護の精神から生まれたわけじゃない。単純に「金になったから」。
人糞は上質な肥料として高く売れた。だから武家屋敷のトイレ使用権を業者が競り落とすなんてこともあった。古紙も、再生すれば商品になる。灰は洗剤や染料の原料。
つまり――捨てるよりリサイクルのほうが儲かるという、極めて合理的な経済システムやったんよ。
■ 「循環社会」の裏側にあったもの
美談だけじゃない。江戸の現実も見ておこう。
- ゴミの不法投棄が絶えず、幕府は何度も「川に捨てるな」とお触れを出してる
- 糞尿の扱いが雑で、夏場は悪臭と衛生問題が深刻やった
- 布団を持てる庶民は綿の出し入れをやってたし、それで裁縫も上達した。ただし全員が布団を持ってたわけじゃない
- 着物のリサイクルも、「もったいない精神」というより新品を買えないから継ぎはぎしてた
つまり、江戸の循環システムは「必要に迫られて生まれた知恵」であって、高い環境意識の産物ではなかった。
■ それでも、学べることはある
とはいえ、江戸のシステムには現代が見習うべき点もある。
1. 「廃棄物」を「資源」として再定義した
ゴミという概念が薄かったのは事実。壊れたものは修理し、使えなくなったものは別の用途に転用する。モノの「終わり」を設定しない文化があった。
2. 地域内で完結する経済圏
都市で出た糞尿は近郊農家が買い取り、その野菜がまた都市に戻る。輸送距離が短く、エネルギーロスが少ない。
3. 修理技術が職業として成立していた
鋳掛け屋、研ぎ屋、提灯張り替え職人…。「直して使う」ことに対価が支払われる社会やった。
■ 平安・江戸・現代、それぞれの循環
平安時代は、そもそも大量生産・大量消費の概念がない。循環というより、モノが少なすぎて使い切るしかなかった。
江戸時代は、100万人都市という規模で循環システムが機能した稀有な例。ただしそれは経済合理性と必要性が生んだもの。
現代は、制度としてのリサイクルは進んだけど、採算が合わないと動かないシステムになってしまった。
■ 美化しすぎず、学ぶ
江戸時代を「エコの理想郷」として美化しすぎる必要はない。 あの時代の人々は、環境を守ろうとしたんじゃなく、生き延びるために工夫しただけ。
でもその「工夫」の中に、現代が忘れかけてるヒントがある。
それは――
「捨てる」を前提にしない暮らしの設計と、「修理」や「転用」に価値を見出す経済の仕組み。
SDGsが目指す未来は、過去の美化された理想の中にあるんじゃなく、過去の泥臭い現実から抽出できる知恵の中にあるんやないかな。
生活編
あの時代、人々はどんな生活をしていたのだろう?衣食住から働き方まで、素朴な疑問にわかりやすくこたえます。