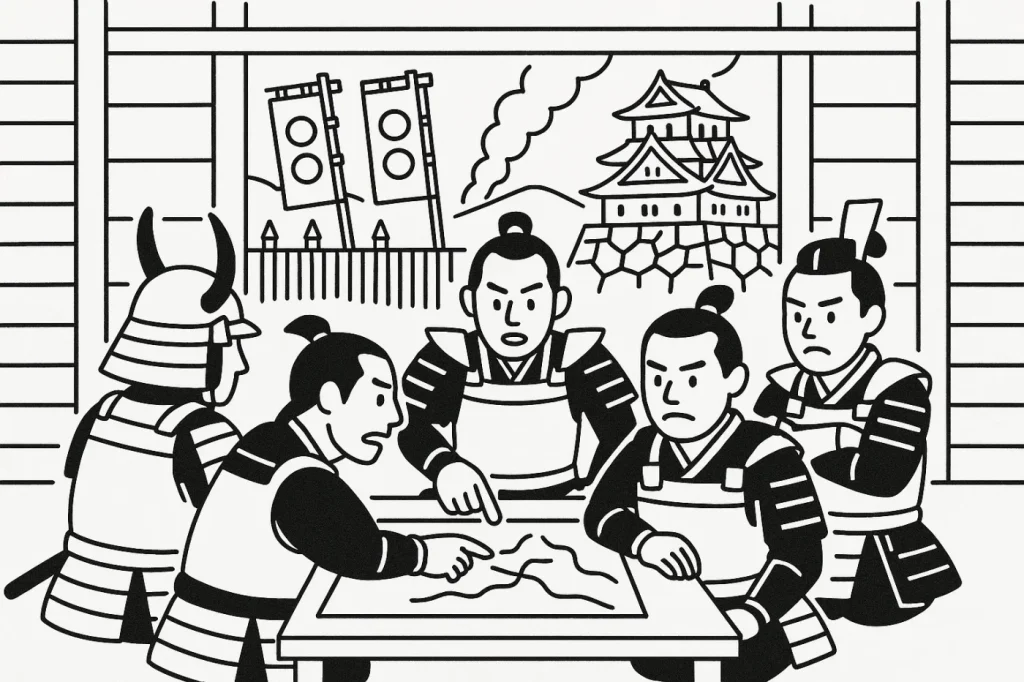戦国時代の軍の構成ってどんな感じやったん? 例えば、兵隊、鍛冶屋職人やワラジ職人?、調理師、スパイ、みたいな感じで構成されてたん?
いいところ突いてるなあ……!
まさに「戦う組織=戦う人だけでは成り立たない」。
実際の戦国軍の構成を見ていくと、「軍勢」というより、ひとつの“移動する町”に近かったんよ。
では、リアルな内訳を描いてみよう。
1. 戦う者(武士・足軽)…全体の2〜3割
まず「戦う人」は意外に少ない。
主戦力である武士・足軽・鉄砲足軽・弓足軽を合わせても、およそ全体の2〜3割ほど。
武士は隊長格で、実際に戦場で槍を振るうよりも、陣立てや采配を担っていた。
足軽は「歩兵」。主に槍・鉄砲を使い、数で押す。
つまり、1万人の軍勢なら、実際に刃を交えるのは3千人前後やね。
2. 兵站・補給部隊(荷駄・炊き出し)…2〜3割
戦国軍のもう半分を支えていたのが、
食と物資のプロたち。
- 荷駄隊(にだたい):米・水・塩・矢・火薬・衣類などを運ぶ
- 炊き出し係:飯を炊く、味噌汁を作る、湯を沸かす
- 馬係(うまかかり):馬の世話・装具の修理
- 医療係:薬草を煎じ、傷を縫う
- 水汲み・井戸掘り係:飲料水の確保
特に炊き出し部隊は重要で、戦が長引くと士気が食事で左右された。
「飯が炊けぬ軍は負ける」とまで言われてた。
3. 職人部隊(鍛冶屋・木工・ワラジ職人)…1〜2割
戦の裏方で欠かせなかったのが職人。
- 鍛冶屋:刀や槍の修理。釘・鎖・針金も作る。
- 木工師:弓・矢・馬具・橋・梯子を作る。
- 革職人:甲冑や草鞋(わらじ)の補修。
- 縄職人:馬の手綱、荷物の結束、仮設柵の構築。
遠征中は「仮設の作業小屋」をつくって、そこが即席の「野戦工房」になった。
この人たちは戦士ではないが、一番頼りにされた“影の武人”やった。
4. 情報・通信係(伝令・忍び・通訳)…1割弱
- 伝令役:各陣を走り回って命令を伝える。
- 忍び(間者):敵情偵察、スパイ、潜入。
- 通訳・交渉人:異国・他国の使者対応。
忍びは伊賀・甲賀など専門集団が多く、単独行動で動いてた。
戦の情報線は、今で言えばインターネットの通信網。
これが切れると、軍全体が盲目になる。
5. 雑兵・雑役(庶民・徴用労働)…3〜4割
戦が始まると、領地の農民も徴発された。
戦わずとも、彼らが
- 塀を作る
- 土塁を積む
- 矢を運ぶ
- 倒れた者を運ぶ
といった雑役をこなした。
この人たちは、兵よりも生活者。
戦を“働きながら生き抜く”人々やった。
6. 「軍勢」とは、“村の総力戦”だった
戦に出るというのは、単に武士が刀を振るうことではなく、領民全体が動く経済活動でもあった。
米を炊く者がいて、
武器を直す者がいて、
祈る者がいて、
初めて軍が立つ。
つまり、軍とは「国の縮図」。
命のシステム全体が動いていたんや。
現代に置き換えるなら
出張先でWi-Fiや電源がないと動けないように、戦国の軍も、職人と食料がなければ動けない。
武士は前線の営業部。
鍛冶屋はエンジニア。
炊き出し隊はバックオフィス。
忍びは情報システム。
戦は、チームワークそのものやったんやで。
参考・参照リンク(戦国時代)
※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。