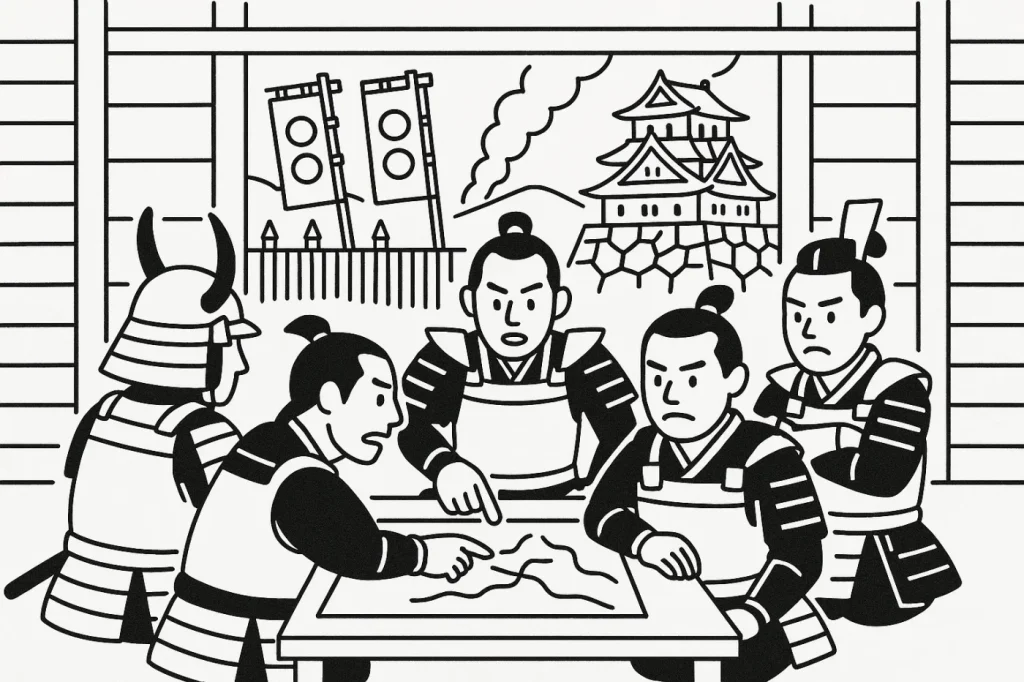車中泊でも1日1回は温泉に入りたいと思うのに、戦場にいる、もしくは行軍してる人たちって、衛生管理はどうしてたん?もちろん洗濯なんてできなかったやんな?髭なんか伸び放題やんな?夏場の戦場での臭いも気になるわ。どうしてたん?
めっちゃリアルな問いやな。
確かに「温泉入りたい…」という現代感覚で考えると、戦国の戦場生活はほぼ極限の不衛生環境やった。
けど、実は当時の人たちも「清潔=健康=戦力維持」と理解してて、
できる範囲で“衛生戦術”を工夫していたんよ。
では、実際の戦場・行軍・籠城の3パターンで見ていこう。
■ 1. 行軍中の衛生管理 ――「水浴び」が風呂の代わり
行軍では、川や湧き水があればすぐに身体を洗うのが基本。
「禊(みそぎ)」や「水垢離(みずごり)」の文化があるから、
単なる汚れ落としではなく、心身の清めの意味もあった。
方法
- 川で頭や手足を洗う(全身は難しい)
- 汗や埃を拭くために手拭(てぬぐい)を常備
- 湯を沸かして“湯拭き”することも(小隊規模の休息地で)
つまり「風呂」ではなく「拭き風呂」。
鉄砲の火薬や汗、血、泥にまみれる中で、これだけでもだいぶマシやったらしい。
■ 2. 戦場キャンプ・陣中の衛生 ――「陣屋の湯」「湯女」の存在
意外にも、戦陣で風呂に入る文化はあった。
特に大将クラスや精鋭部隊には、野戦風呂(陣中湯)が設けられた。
- 釜で湯を沸かし、桶や樽に入れて入浴
- 城下や温泉地が近ければ、温泉を利用
- 有名なのが真田軍が使った信州の温泉(別所・戸倉など)
- 戦国の“温泉リゾート”は実は湯治+軍略でもあった
また、戦地に「湯女(ゆな)」=風呂係の女性を同行させることもあった。
彼女たちは洗濯・炊事・看護などを兼ねて、兵の心身を癒やした。
→ 現代でいえば「移動式風呂トレーラー+看護チーム」みたいなもんやね。
■ 3. 髭・頭・虫対策 ――「髭は威厳」「頭は剃る」「虫は灰と香で」
髭
髭は戦国武将の「威厳の象徴」。
剃るというより、整える程度。
信玄・謙信・家康などの肖像も、立派な髭を蓄えてるやろ。
ただし、兵卒は伸び放題。
夏の長期戦では「髭も汗も虫も一緒に抱えて生きる」状態。
頭髪
戦闘前には月代(さかやき)=頭頂部を剃る。
これは武士の身分証でもあり、衛生的理由もあった。
汗や虫の巣を防ぐ意味で、定期的に剃刀を持つ者がいた(髪剃衆)。
虫対策
- 衣服の縫い目や髪に灰・煙草の灰をすりこむ
- 香(蚊取り線香の原型)を焚く
- 虫除けに“ドクダミ・ヨモギ・ニンニク”を腰に吊るす
江戸期の記録では、夏場に兵の体臭・虫刺され対策で「線香を腰につける」習慣もある。
■ 4. 衣類と洗濯 ――「干す」「焼く」「叩く」で済ませた
洗濯はほぼ不可能。
水場を占有すると命取り(敵に見つかる・感染)になるからね。
代わりに:
- 汗を吸った小袖や下帯を天日に干す
- 汚れた服を叩いて埃を落とす
- 虫が湧いたら焚き火で軽くあぶる(消毒代わり)
戦後に城下でようやく洗濯・入浴する。
つまり、「戦時中は耐える」「戦後に整える」というリズム。
■ 5. におい・汗・死臭との共存
ここが一番リアルな部分や。
戦場は、血・汗・糞尿・火薬・死体の臭いが混じる“地獄の臭気”。
夏場の合戦(特に長期戦)では、記録にこうある:
「夏の陣中は、腐臭にて息を保ちがたし」
「馬も人も、同じ蒸れた皮の臭いす」
兵は鼻を布で覆ったり、香草(丁子・白檀)を身にまとう。
上級武士は香木を焚き染めた兜袋や鎧下を着てた。
(これが「武士の香り文化」の起源でもある。)
■ 6. 医療・感染対策(いま風に言えば衛生兵)
当時、戦場感染症は死因の筆頭。
赤痢・破傷風・疥癬・シラミ熱などが多発。
だから各軍には医師(医僧・薬師)が同行してた。
- 傷口は酒・味噌・灰で殺菌
- 熱病にはヨモギ湯や薬草風呂
- 「湯治場」=軍病院的役割も兼ねる
→ 戦国の温泉地(有馬・別所・道後など)は、実は医療拠点+保養地としても機能してた。
■ 7. 戦国の“衛生観”まとめ
| 項目 | 実態 | 工夫・代替法 |
|---|---|---|
| 入浴 | ほぼ川・桶湯・湯拭き | 陣中湯・温泉利用 |
| 髭・髪 | 髭は誇り、頭は剃る | 剃刀・油 |
| 虫 | 常時つきまとう | 灰・香・薬草 |
| 衣類 | 洗えず、干して叩く | 火で殺虫・乾燥 |
| 匂い | 常時ひどい | 香木・薬草・煙 |
| 病気 | 赤痢・破傷風 | 酒・灰・温泉・祈祷 |
■ 結論:「風呂に入れぬ武士は、風と煙で身を清めた」
戦国の兵たちは、
- 川で洗い
- 火で乾かし
- 香でごまかし
- 祈りで整えた。
つまり、「清潔」とは体を洗うことではなく、“穢れを祓う心構え”やった。
行軍の汗と土の匂いは、戦士の勲章。
その延長に、現代の“温泉文化=癒しと再生の場”が生まれたんや。
次は「戦国の温泉文化」──たとえば信玄の湯治場や武将たちが愛した温泉地(別所・下呂・有馬・道後など)を、まとめてみよか?
参考・参照リンク(戦国時代)
※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。