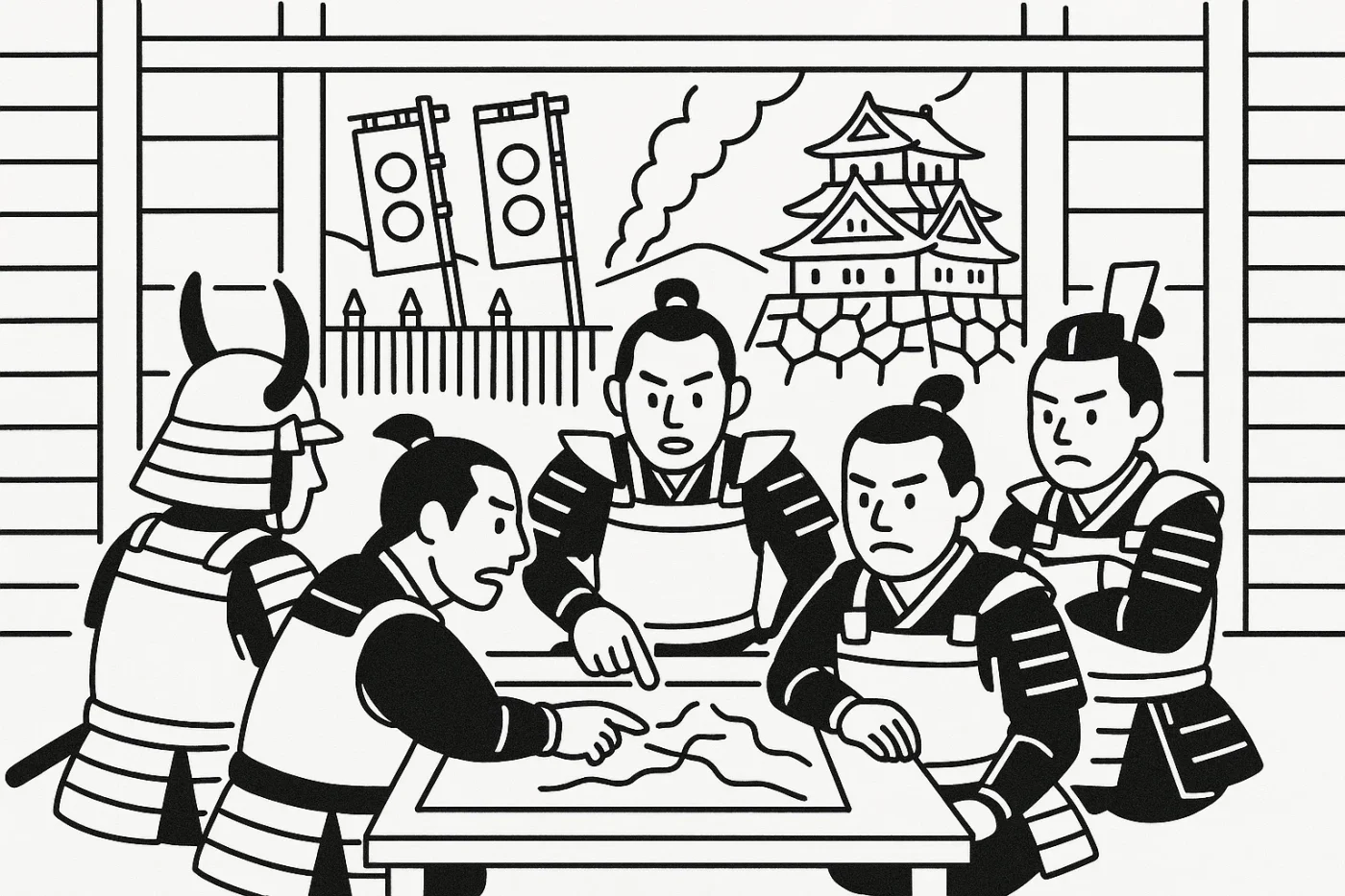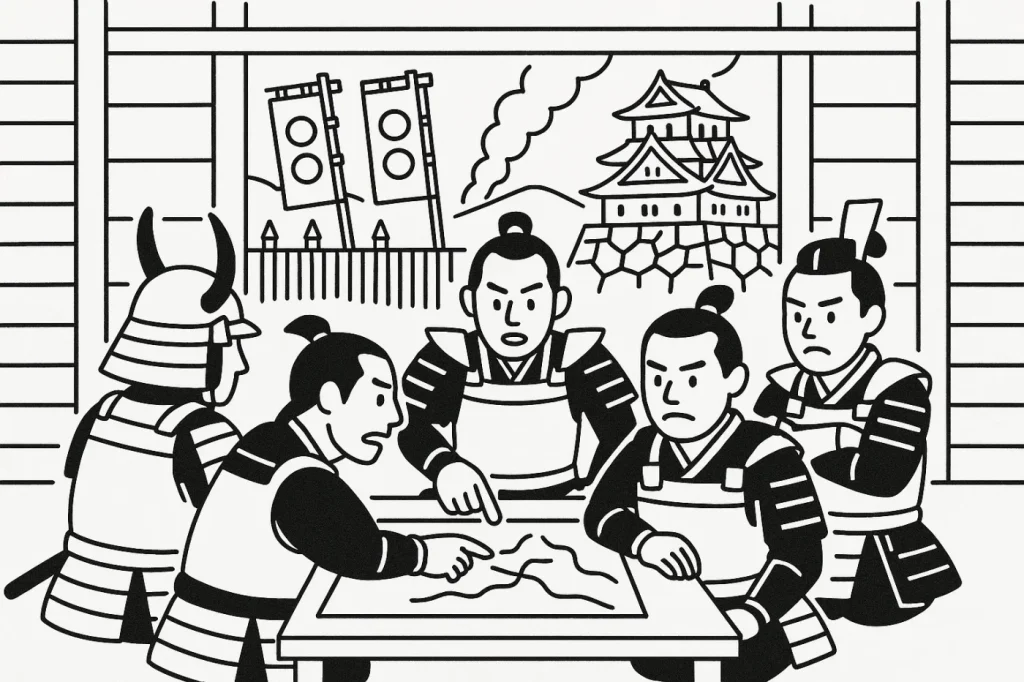籠城戦って、城内では、どんな生活してたん?飯とはトイレは?
多くの人は「城で敵を待つ」イメージを持つ。 でもホンマは、外の敵よりも内の飢えと病との戦いやったといえる。
城の内と外:二つの地獄
籠城戦は、外の敵よりも内の飢えと病との戦いだった。
外は攻撃・包囲で危険だが、内は逃げ場のない密室社会。
- 城外では、田畑や町は敵の兵火で焼かれ、住民は城へ避難。
- だが、もともと城は「戦時用の居住空間」ではないため、想定以上の人員が入ると即飽和。
- 一夜城や山城では水源の確保が死活問題で、堀や井戸を持たない城は短期戦前提。
たとえば上田城(真田昌幸)では、川の水を引き込んで防御・給水両方を確保していた。
最初の課題は「兵糧(ひょうろう)」。
籠城前にどれだけ蓄えられるかで命運が決まる。
- 主食は米・麦・雑穀。保存用に干飯(ほしいい)や味噌玉を大量に作る。
- 魚や肉は塩漬け、干物。
- 野菜は干し大根・漬物などで補給。
- 飲料水は井戸・雨水・溜池。だが井戸を毒で汚されることもあり、「水番」が常駐。
長期戦になると「馬肉」「皮」「草」「木の皮」までも食べる。
1580年の鳥取城の籠城(羽柴秀吉の兵糧攻め)では、餓死が相次ぎ、人肉に手を出す者まで出たと記録にある。
便と衛生
現代感覚では想像を絶するが、排泄は大問題。
- 城の中では糞尿処理が追いつかず、堀や川に流す。
- だがそれが水源を汚染し、疫病の原因にもなる。
- 夏場は悪臭が充満し、ウジや蚊が大発生。
- 清掃係(城奉公人・足軽・女中など)は、命がけの衛生維持部隊でもあった。
梅雨や夏季には赤痢・腸チフス・食中毒が蔓延。
皮膚病やシラミも常態化していた。
男と女、年寄りと子供
籠城は「村ごとの避難」なので、女性や子供も多く城内にいた。
- 女は炊事・水汲み・看病・矢玉拾い(再利用)などに従事。
- 老人や子供は倉庫や蔵に隠れるが、心理的負担が大きく、恐怖や飢えで衰弱。
- 夫を失った女たちが戦後に「落城後の再建」を担った例も多い。
例:山中城落城後の農村女性が、再耕作して生活再建をした記録が残る。
怪我と治療
医療は乏しく、戦傷者は多くが感染で命を落とす。
- 傷口は焼灼(やいしゃく)や灰・味噌・酒で消毒。
- 湿布代わりに草や薬草(ヨモギ、ドクダミ)を使う。
- 腕や足の切断も珍しくなかったが、麻酔がないため気絶するまで痛みとの戦い。
- 傷病兵の看護は、主に女性が担当。
修理と改築(戦中メンテナンス)
攻撃を受けながらの修理は常に行われた。
- 壁の穴は土嚢や板で即修復。
- 石垣が崩れたら、夜間に農具で積み直し。
- 木材は内部建物を壊して転用することも多い。
- 矢倉や塀の屋根は、敵の火矢に備え水をかけて湿らせておく。
籠城が長期化すると、まるで「修繕をしながら沈む船を守る」ような状態になる。
武器・物資の調達
外からの補給が断たれるため、リサイクル戦法が主流。
- 敵の矢を拾って再使用(矢拾い係=命がけ)。
- 矢羽根の交換、火縄の節約。
- 鉄砲は弾薬が尽きるため、戦初期に集中使用、後半は温存。
- 火薬は内部で調合もするが、原料(硝石)が乏しく、城内で小規模生産した記録もある(例:島原の乱)。
落城と再起
籠城戦の末期は、命の選別が始まる。
- 殿様が自害する前に、女・子供は自刃、または逃がされる。
- 敵方の慈悲を期待して白旗を掲げて開城する場合も。
- ただし落城後の略奪・凌辱は避けがたく、「最後まで戦う」覚悟が尊ばれた。
- しかし、後に再起した例も多く、上田城の真田昌幸・熊本城の加藤清正(再建)などは象徴的。
まとめ:籠城とは「共同体の耐久実験」
籠城戦は、単なる戦術ではなく「生存と秩序の実験場」やった。
人間がどれほどの極限で、秩序を保ち、助け合い、再建するか。
外敵との戦いより、内部崩壊を防ぐことが勝利の条件やった。
参考・参照リンク(戦国時代)
※本カテゴリの記事は上記の公的史料・展示情報を参考に再構成しています。